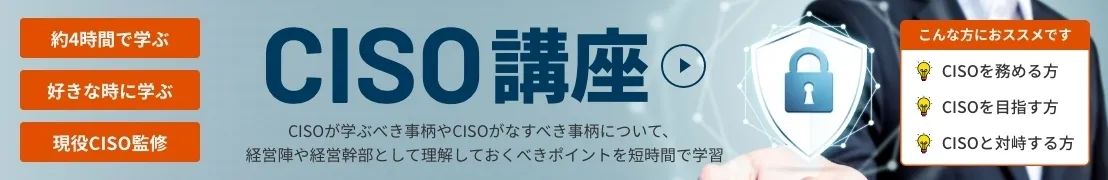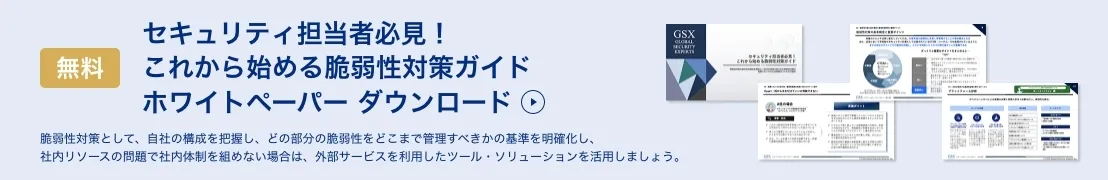Webアプリケーション診断
Webアプリケーション/Web APIの脆弱性診断を行い、Webサイト経由のサイバー攻撃に対する弱点がないかを診断するサービスです。ツールと手動による検査を併用し、精度の高い脆弱性診断を実施します。IPAで示されている脆弱性を診断項目として網羅し、システムへの影響、起因する障害発生について最大限に配慮して診断を実施します。
Webアプリケーション診断をお急ぎなら最短3日の「Web脆弱性診断クイック」で対応します。
サーバやネットワーク機器の脆弱性診断は「プラットフォーム診断」にて承ります。
Webアプリケーション/Web APIの脆弱性診断を行い、Webサイト経由のサイバー攻撃に対する弱点がないかを診断するサービスです。ツールと手動による検査を併用し、精度の高い脆弱性診断を実施します。IPAで示されている脆弱性を診断項目として網羅し、システムへの影響、起因する障害発生について最大限に配慮して診断を実施します。
Webアプリケーション診断をお急ぎなら最短3日の「Web脆弱性診断クイック」で対応します。
サーバやネットワーク機器の脆弱性診断は「プラットフォーム診断」にて承ります。
情報漏洩
Webサイト改ざん
不正アクセス・乗っ取り
サービス停止・業務妨害
法規制・コンプライアンス違反
※IPA(独立行政法人情報処理推進機構)「安全なウェブサイトの作り方」
診断を実施するエンジニアはセキュリティ資格保持者で、最新・最先端のハッキング技術を有しています。
-

多様な診断対象への対応、豊富な診断メニュー
- お客様のご要望に応じて、コストメリットの高いプランをご提案します。
- Webアプリケーションだけでなく、スマホネイティブアプリ、クラウドなどの脆弱性診断にも対応。PCクライアントアプリ等の特殊なアプリ、IPv6などへの診断も実施可能です。
- インターネット経由、オンサイト診断、夜間や休日を利用した診断など、診断方法や場所(リモート/オンサイト)もご相談に応じます
-

診断後の具体策を総合的にご提案
- WebアプリケーションファイアウォールやIDS/IPSといった製品のご提案
- 脆弱性診断の社内実施体制を構築する脆弱性診断ツールの販売・使用トレーニング
- セキュリティ人材の育成・資格取得サービス
- セキュア開発ガイドライン作成
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」に登録
01|お見積り・ご発注
診断対象などを選定の後、お見積書を作成します。診断期間や対象などを決定の上、お見積内容に基づき、ご発注いただきます。
02|事前調整・内容確認書作成
診断内容確認書を作成します。必要に応じて事前の導通確認など細部の確認を行います。スマホアプリ診断の場合、対象ファイルをお預かりします。
03|診断
ご指定の時間帯で診断作業を行います。基本は、平日日中(10時~18時)です。夜間、休日をご希望の場合は、ご契約前にお申し付けください。
04|速報
診断中に緊急度の高い脆弱性が発見された場合、速報としてご連絡します。※ご要望の場合のみ。ご契約時にご依頼ください。
05|結果分析/報告書作成
診断結果を報告書として取りまとめ、納品いたします。※診断終了後10営業日以内
06|報告会
専門エンジニアが内容を説明する報告会を開催します。
07|再診断
脆弱性が検出された箇所をお客様側で改修された後、同様の脆弱性が検出されないかを再度診断します。
Webアプリケーション診断
| No. | 診断項目 | 危険度 | ツール | 手動 | IPA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
セッション管理の不備 |
高 |
○ |
✔ |
|
2 |
セッションフィクセーション |
中 |
○ |
○ |
|
3 |
クロスサイトリクエストフォージェリ |
中 |
○ |
○ |
✔ |
4 |
クロスサイトスクリプティング |
高〜中 |
○ |
○ |
✔ |
5 |
クリックジャンキング |
中 |
○ |
○ |
✔ |
6 |
SQLインジェクション |
高 |
○ |
○ |
✔ |
7 |
OSコマンドインジェクション |
高 |
○ |
○ |
✔ |
8 |
ディレクトリトラバーサル |
高 |
○ |
○ |
✔ |
9 |
SSIインジェクション |
高 |
○ |
○ |
|
10 |
XMLインジェクション |
高 |
○ |
○ |
|
11 |
XPathインジェクション |
高 |
○ |
○ |
|
12 |
XQueryインジェクション |
高 |
○ |
○ |
|
13 |
LDAPインジェクション |
高 |
○ |
○ |
|
14 |
MXインジェクション |
高 |
○ |
✔ |
|
15 |
HTTPレスポンスの分割 |
高 |
○ |
○ |
✔ |
16 |
リモートファイルインクルード |
高 |
○ |
○ |
|
17 |
通信の暗号化 |
中 |
○ |
○ |
|
18 |
証明書の不備 |
中 |
○ |
||
19 |
Referrerによる情報漏洩 |
中 |
○ |
||
20 |
ユーザID等の調査 |
中 |
○ |
✔ |
|
21 |
詳細なエラーメッセージ |
低 |
○ |
○ |
|
22 |
拡張子偽造 |
高〜低 |
○ |
||
23 |
コメント・デバッグ情報 |
高〜低 |
○ |
○ |
|
24 |
アプリケーション固有の問題 |
高〜低 |
○ |
||
25 |
フォーマットストリング |
高〜低 |
○ |
○ |
|
26 |
バッファオーバーフロー |
高〜中 |
○ |
○ |
✔ |
スマートフォン向けWebアプリケーション診断
主な診断項目(一部抜粋)
SQLインジェクション
クロスサイトスクリプティング
ディレクトリトラバーサル
セッション管理の不備(パラメータ改ざん等)
クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)
他ユーザーへのなりすまし
セッションフィクセーション
通信の暗号化の不備
証明書の不備 など
診断の実施場所
診断の実施可能日
報告書(例)